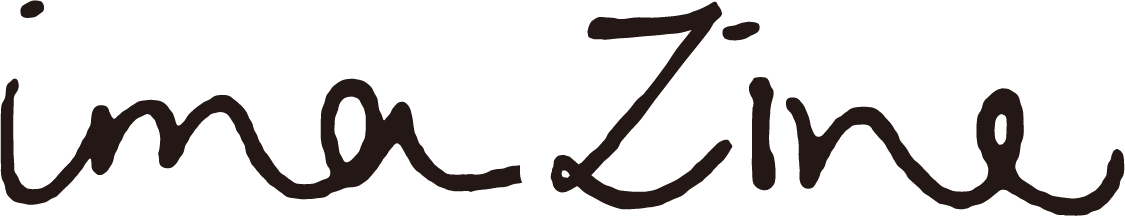[VOL.29]
粟沢観音 | 八十八夜祭
TEXT BY TANAKA YUKIKO
毎年五月二日、茅野市玉川の粟沢観音では「八十八夜祭」が開かれる。この茅野の地でも桜の季節が終わりを告げ、近づく初夏の足音に心躍る季節。本尊へと続く急な石段を登った先には、夜店が並び、人が溢れる。長い冬を終えた喜びと五穀豊穣、家内安全の願いを胸に、多くの人が石段を登っていく。

古くから続く観音様と夜祭
粟沢観音は戦国時代に建立されたとされ、馬頭観世音菩薩を本尊とし、諏訪八十八ヶ所札所の八十七番札所にもなっている。毎年五月二日に行われる「八十八夜祭」では、五穀豊穣や家内安全を依願する護摩法要などが行われ、賑わいを見せる。祭の歴史も古く、その発祥は明治時代とも江戸時代とも言われている。
甲州街道や大門街道とも近かったことから、交易や農耕による発展を祈念する人々が、茅野市内はもとより、伊那地方や山梨など近隣の県からも多く訪れたという。

現代においての「八十八夜祭」は、夜店がたくさん並ぶお祭りとしても認知されていて、心待ちにしている市民も多い。かくいうイマジン編集部のスタッフも、そのほとんどが幼少期にこのお祭りに出かけた経験を持つ。
普段は静かな境内が、この日だけは屋台や遊びに来た人でぎゅうぎゅう詰めになる異世界感。暗くなっても友達と遊べる特別感は今思い出しても胸が高鳴るものだ。小遣いを握りしめ、はやる気持ちを抑えながらどこの夜店で何を買うか真剣に吟味する。わたあめにクレープ、りんご飴か焼きそばか。はたまた射的や金魚すくい…さあどうしよう。
提灯の明かりに照らされた新緑の下で、他校の子たちとすれ違ったり、茅野市中の子どもたちが一堂に集まっているのではないかと思うような混雑に身を委ねたりしていることが、ちょっぴり緊張というスパイスをもたらすのもまた一興。そうして祭りは、二十一時ごろまで続いていくのだ。
お話しを伺った粟沢区社寺運営委員会の方は、「昔は車じゃなかったから、参拝客の列がずらーっと本町の方まで伸びていたらしいです。遠方から電車で茅野駅にきて、歩いてここまで来ていたから、途中買い物する人なんかも多くて、本町の商店街が賑わっていたみたいですね。」と話してくれた。
最近でこそ遠方から来る人は減ったというが、それでも諏訪や岡谷からくる人も多く、一夜で数千人が訪れる年もあるという。

祭りがつなぐ思い出と未来
子どもだった私たちも、大人になり、親となった。小さなわが子の手を引いて再び訪れたとき、石段の一段一段を一生懸命に登る姿に、その高さや長さを改めて実感した。石段を上り切った子どもは、満足そうな顔で屋台の合間を歩く。一つひとつ覗き込んでは目を輝かせているのを見ていると、かつての自分もこんなふうだったのかと思う。大人の自分にはかつてのような高揚感はないけれども、こうして思い出はつながり、また誰かの新たな思い出となっていくのだ。
茅野には他にも「茅野どんばん」を筆頭に地域ごとのお祭りもたくさん存在する。時代は変わっていく。桜の咲く時期もずれていく。それでも祭りは残ってほしい。そして共に生きる人々の思いをこれからもつなぎ、紡いでいってほしい。


I N F O R M A T I O N
粟沢観音 八十八夜祭 毎年5月2日開催