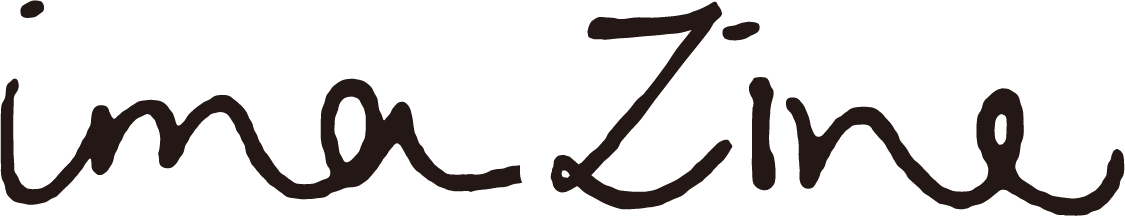[VOL.11]
定正|小尾幸太郎さん

TEXT BY TANAKA YUKIKO
PROLOGUE
言刀や包丁、大工道具に農具。昔から日本人の生活を支えてきた刃物たち。それを生み出してきたのが鍛冶屋である。ここ諏訪にもかつては多くの鍛冶屋があったが、手軽に扱える刃物が増え、使い捨ての時代の台頭ととともにその数は減っていく。現在諏訪地区に唯一残る鍛冶屋「定正」。定正では、そんな時代の流れに抗うように、新たなブランドを立上げようとしている。暮らしの中で、街の中で、鍛冶屋はどんな立ち位置を目指すのか。3代目で代表取締役の小尾幸太郎さんにお話を伺った。
鍛冶屋の火を灯し続ける
創業は大正9年。もともと鍬や鎌を作る野鍛治で、昭和44年にはここに金物屋の店舗をオープンしました。当時は鍛治職人も6~7人いたと思います。もともと家業を継ぐつもりではいましたが、自分が職人になるというよりはこのお店を受け継ぐというイメージでした。当時は茅野市内にも何件か鍛冶屋はありましたが、今はもううちだけ。しばらくしたらぼくは引退して、長男が社長として、次男が鍛冶職人として受け継いでくれることになっています。
御柱祭で使う斧(よき)も作っています。斧は御柱を山から切り出す際や木落の追いかけ綱を切るとき、建て御柱の冠落としなど、重要な場面で使われるんです。反面実用性という意味では使う人はほとんどいなくて、これからも使われることはないでしょう。
御柱祭で使う斧のうち、うちが作っているのはほんの一部ですが、それでも昨年も50〜60本は作ったんじゃないでしょうか。地元にはもう他に鍛冶屋はありませんから、次男が継いでくれたおかげでこれからも斧が作れる。次回もその次もまだまだ作れるっていうのはうれしいですね。
本物の、本当の意味
いま包丁のブランドを立ち上げる準備をしていて、この春には発売を予定しています。包丁ってやはり生活に一番根ざしたものですから、ちゃんとした包丁をブランディングして、作って、売っていくべきなんじゃないかと考えたんです。それでもいまは安い量産品がたくさん出回っていますから、気軽に使ってもらいたいという思いと、その中で利益を出していかないといけない現実、その間で悩みながら、というのが正直なところですけどね。
だって、量産品がなくなることはないでしょう? でも量産品には量産品の良さがあるからそれはそれでいいんです。ただ本来は、どの家でも包丁は研いで長く使っていたんですよね。
包丁とは違うけれど大工さんなんかはノミやカンナといった刃物を自分で研ぎます。仕事の作業時間よりも刃物を研ぐ時間の方が長くかかるっていわれるくらい時間をかける。そこまでこだわらないにしても、本物の刃物を一本でもいいから持ってもらって、「本物の刃物の切れ味」とか「メンテナンスをすれば長く愛着を持って使えるものだ」といった感覚を知ってもらいたい。うちでは研ぎも請け負います。包丁という物を売るのはもちろん、「大切に長く使うこと」を生活の一部にしてほしいんです。
暮らしの一員、街の一員としての“モノ”
茅野市内の飲食店さんはみんなうちの包丁を使ってるんだよ、っていうくらいになったらいいなって思いますね。いい飲食店がたくさんありますから、食材だけじゃなくぜひ包丁も地元で作られたものを使って欲しい。街の中で斧っていうのは、祭事という場での、ある意味その地の人々の精神を支えた、単なる物としてだけではない役割があるものだと思うんですけど、包丁もまた別の意味でそういう風になっていくといいですね。暮らしの一員、街の一員とも感じられる存在になっていってほしいと思っています。
I N F O R M A T I O N
定正
〒391-0003
長野県茅野市本町西22-9
TEL 0266-72-2530